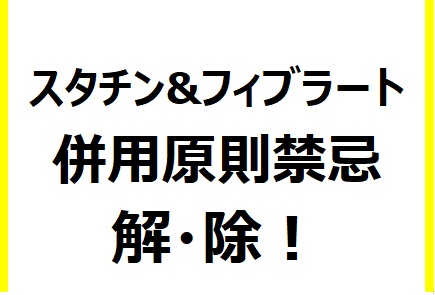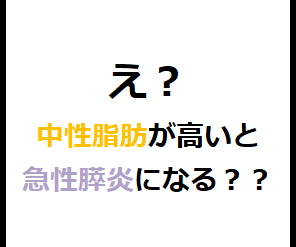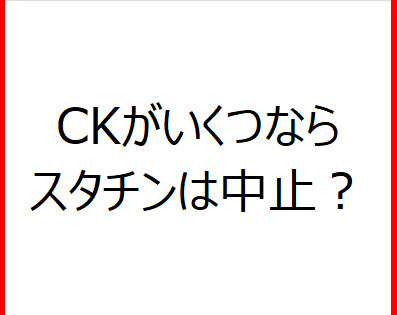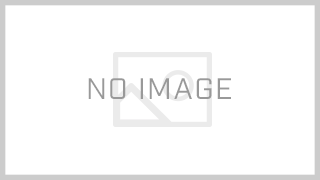脂質異常症治療のスタチンは心血管保護薬だ
HMG-CoA還元酵素阻害薬であるスタチン系は、血液中のコレステロール、特にLDLコレステロール(悪玉コレステロール)を下げる効果を発揮し、脂質異常症(昔の呼び方だと高脂血症)の治療に広く使われるメジャーな薬だ。
スタチン系のすごいところは、ただ単にコレステロールを下げることだけではない。
動脈硬化の進行を抑え、心筋梗塞や脳卒中といった心血管疾患のリスクを減らすことだ。
このことから、スタチン系は「心血管保護薬」として高く評価されている。
スタチン系の糖尿病リスクについて
心血管疾患のリスクを下げる一方で、近年、スタチン系薬剤の使用が新規発症糖尿病(NODM)のリスクを上昇させる可能性が指摘されている。
Lancetに2010年に掲載された研究(Lancet. 2010 Feb 27;375(9716):735-42.)によると、複数の臨床試験を統合して解析した結果、スタチン系薬剤の使用で糖尿病を発症するリスクが9%上昇する可能性があると報告されている(オッズ比[OR]1.09;95%CI 1.02-1.17)。
糖尿病発症のメカニズムは複雑だが、主にインスリン抵抗性の亢進やインスリン分泌障害が関連していると考えられている。
また、スタチン系薬剤の投与量が多いほど、糖尿病を発症するリスクが高まる傾向があるようだ。
スタチン系の心血管疾患予防のメリットは依然として大きい
では糖尿病の新規発症リスクがあるなら怖くて使えないじゃないか!と思いたくなるが、実はそうでもない。
スタチン系服用に伴う新規発症糖尿病が心血管イベントを増加させると仮定しても、スタチンそのものによる心血管イベント減少効果の方がベネフィットが大きいのだ(Lancet 2016; 388: 2532-2561)。
日本動脈硬化学会などによる「スタチン不耐に関する診療指針2018」にも、
「糖尿病を新規発症したり、耐糖能が悪化した場合でもスタチンによる心血管イベント抑制効果が上回るため、投与を中止することは勧められない」
と明記されている。
スタチン系薬剤の種類・投与量と糖尿病発症リスクの関係
アトルバスタチン(リピトール®)
●高用量(40~80mg)で糖尿病発症リスクが上昇する可能性が報告されてる。
●アトルバスタチン80mgやロスバスタチン20mgは、アトルバスタチン10mg、シンバスタチン20~40mg、プラバスタチン40mgなどの中用量のスタチンと比較して、糖尿病発症リスクが高い可能性がある(PMID:25887679)。
●アトルバスタチン40mgでも、糖尿病発症のリスクが上昇する可能性が示唆されている(PMID:34433298)。
●プラバスタチン10mg/日と比較した後ろ向き研究では、アトルバスタチン10mg/日投与群でのみ、3ヶ月後にHbA1c(ヘモグロビンA1c)が有意に上昇した(Takano T, et al:J Atheroscler Thromb. 2006;13 (2):95-100.)。
ロスバスタチン(クレストール®)
●高用量(20mg)で糖尿病発症リスクが上昇する可能性がある(PMID: 25887679)。
●プラセボと比較した研究では、ロスバスタチン20mg/日は、糖尿病発症リスクが25%増加した(Am J Cardiol. 2013 Apr 15;111(8):1123-30)。
シンバスタチン(リポバス®)、フルバスタチン(ローコール®)
●現在、糖尿病発症リスクとの関連性や具体的な投与量に関する信頼性の高い情報を確認中です。
プラバスタチン(メバロチン®)
●プラバスタチン40mg/日群とプラセボ群で新規糖尿病発症を比較したところ、プラバスタチン投与によって糖尿病発症リスクを30%低下させた(2002年に発表されたWOSCOPSのサブ解析)。
●プラバスタチン40mg/日は、プラセボと比較して新規糖尿病発症リスクが最も低かった(オッズ比1.07、95%信頼区間0.86〜1.30)(Am J Cardiol. 2013 Apr 15;111(8):1123-30)。
ピタバスタチン(リバロ®)
●アトルバスタチン10mg/日との比較試験では、ピタバスタチン2mg/日の方がHbA1cをわずかに低下させる傾向が報告されている(Mita T, et al:J Diabetes Investig. 2013;4(3): 297-303.)。
●ピタバスタチン1mgと4mgの比較では糖尿病の新規発症に有意差は認めなかった(スタチン不耐に関する診療指針2018)。
●アトルバスタチン、ロスバスタチンの高用量は新規糖尿病発症リスクあり!
●プラバスタチンは高用量でもリスク低い。もしくは糖尿病発症リスクを下げる?
●ピタバスタチンはHbA1cを下げる可能性あり&投与量による糖尿病発症リスクに相関見られず。
最新の知見:大規模なメタアナリシスからの報告(2024年)
The Lancet Diabetes & Endocrinology」(2024 May;12(5);306-319.)に掲載された最新のメタアナリシスによると、
●低~中用量のスタチン療法を受けた患者では、プラセボ群と比較して糖尿病の新規発症リスクが10%高かった(発生率比[RR]:1.10、95%信頼区間[CI]:1.04~1.16)。
●高用量のスタチン療法を受けた患者さんでは、プラセボ群と比較して糖尿病の新規発症リスクが36%高かった(RR:1.36、95%信頼区間[CI]:1.25~1.48)。
このメタアナリシスでは、スタチンを使用すると糖尿病の新規発症リスクは増加するものの、その多くはベースラインの血糖値が高い人であったと報告されている。また、患者全体として見ると、心血管疾患リスクの減少という大きなメリットが得られるため、スタチン治療の利益は糖尿病のリスク増加よりも大きいと結論付けられている。
結論
スタチン系薬剤による新規糖尿病発症リスクはあるものの、心血管疾患の予防効果がそれを上回るため、過度に心配する必要はない。
特に日本では高用量の使用が欧米に比べて少ないため、スタチンの利点は依然として大きいと言えるだろう。
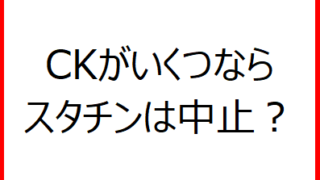
●Xをやっています!【くすりカンパニー】。
「お仕事の依頼」・「当サイトに記事を載せたい方」・「当サイトの記事を使いたい方」・「当サイトをご支援していただける方」を募集中!DMにてご連絡ください。